先日、こどものプログラミング教室を見学してきました。
タブレットから指示を出してロボットを動かします。
思うように動かないことも多く、試行錯誤の連続です。
でも、その過程こそが一番の学びだと感じました。
■ 試行錯誤の連続が成長を生む
プログラミングは、少しずつ修正して目標に近づいていく世界。
一度でうまくいくことはほとんどなく、失敗を重ねながら進んでいきます。
「なぜ動かないんだろう?」
「どこを変えたらうまくいくかな?」
そんな問いを繰り返すうちに、自然と考える力や粘り強さが育っていくのだと思います。
■ 条件制御の大切さ
プログラムの世界では、「条件」をしっかり管理することが大事です。
同じ条件で動かさなければ、どこを直したのか、何が原因なのかが分からなくなります。
条件をそろえた上で、少しずつ動作を変えて確認していく。
地道な作業ですが、これがトラブル解決や精度の高い成果につながります。
■ 一つずつ変えるという基本
プログラムを修正するときは、一度にたくさんの部分をいじらない。
一つだけ変えて、結果を確認して、また次へ。
この「一つずつ確かめる」という積み重ねが、確実な成長を支えているように見えました。
焦らず、順を追って進める姿勢は、どんな学びにも共通する基本ですね。
■ 観察する力を育てる
そして何より大切なのが「観察」。
どのポイントを変えればプログラムが完成するのかは、結果をよく観察することで見えてきます。
動き方や反応を注意深く見ることで、原因と結果のつながりが少しずつ分かっていく。
これは、プログラミングに限らず、人生のあらゆる場面でも役立つ力だと感じます。
■ トライ&エラーが教えてくれること
トライ&エラーを繰り返すうちに、子どもたちは「失敗=悪いこと」ではないと学びます。
むしろ、失敗こそが次の一歩のヒントになる。
その繰り返しの中で、根気・論理的思考・観察力が自然と育っていく。
プログラミングって、単にコードを書く技術ではなく、「考える力」を鍛えるトレーニングなんだなと改めて感じました。
コツコツと、少しずつ。
失敗しても前に進む、その姿がとても頼もしかったです。
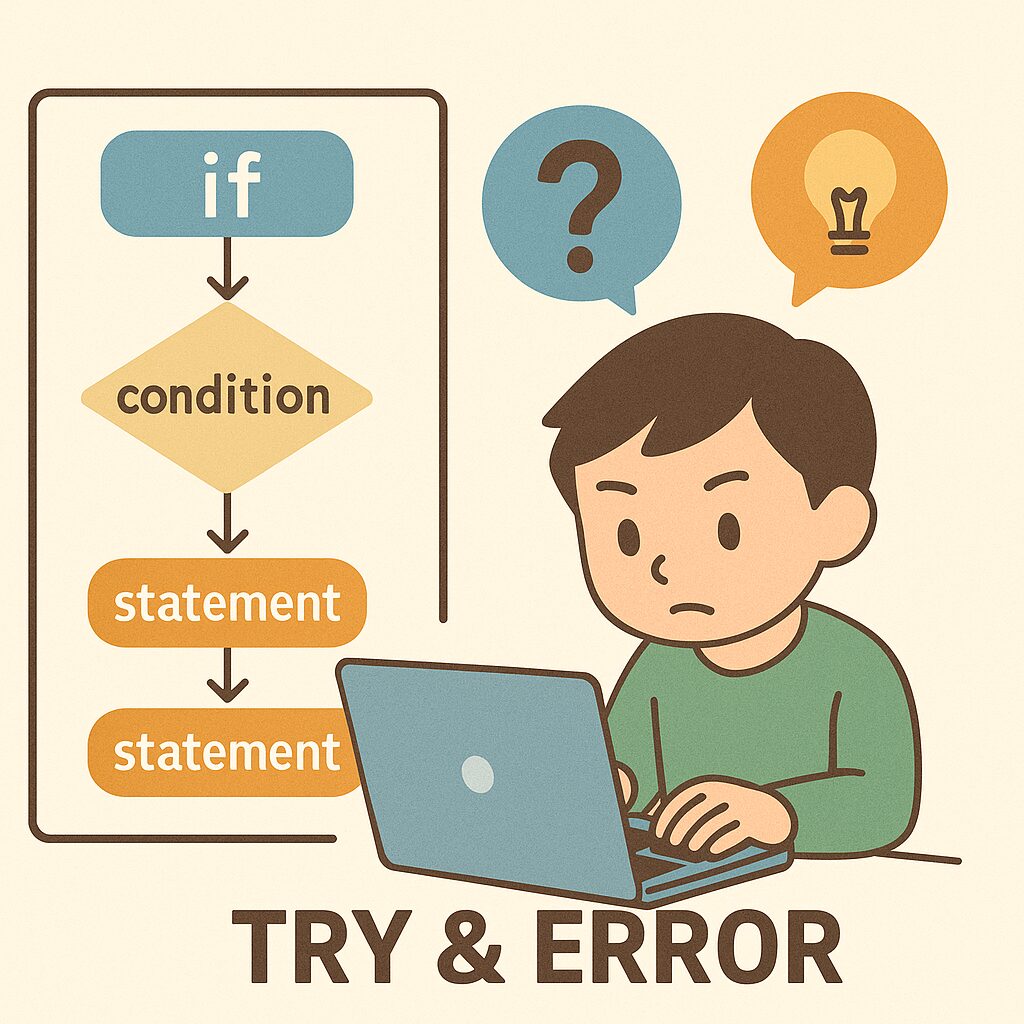


コメント